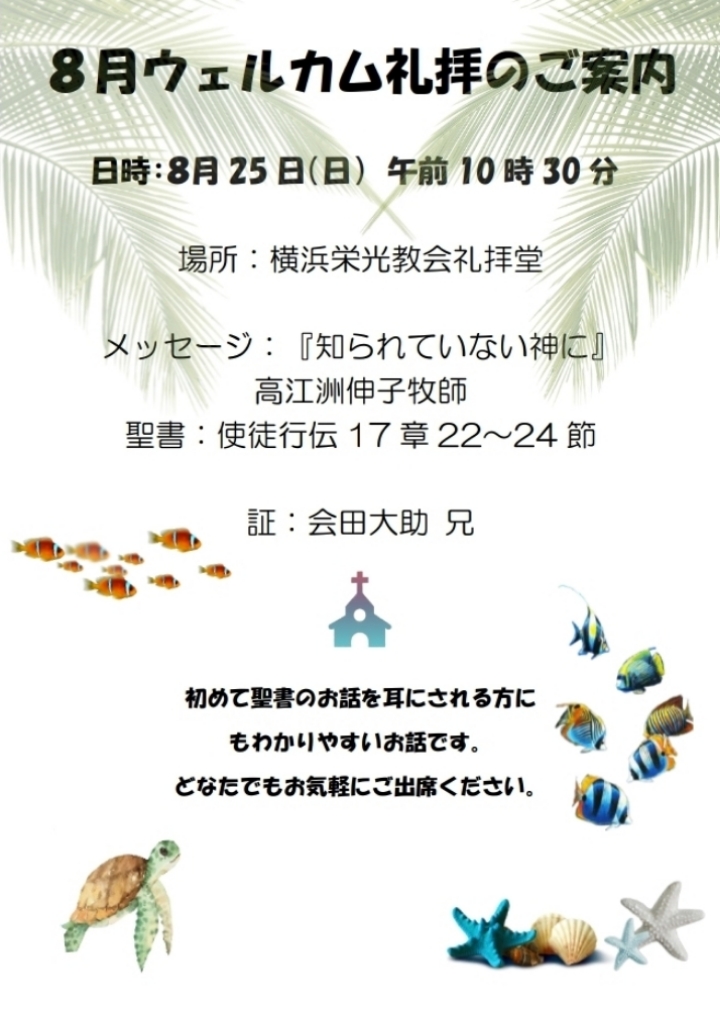『知られていない神に』
聖書 :使徒の働き17章22-24節(新p270)
メッセンジャー:高江洲伸子師
古代ギリシアの宗教について、ウィキペディアは、「多神教である [4] 。神々には序列があり、主神ゼウスが他の全ての神々を支配する王とされた。」と書き出しています。古代ギリシャには多くの神々が祀られていました。にもかかわらず、「知られていない神に」と、更に神を求めているとはどうしたことでしょう。
「人間は考える葦である」と言った、数学者で哲学者のパスカルは、「すべての人の心には神の形をした空洞があり、いかなる被造物によっても埋めることはできない。この空洞を埋めることができるのは、イエス・キリストを通して啓示された創造主なる神のみである」と言っています。アテネで「知られていない神に」と刻まれた祭壇を発見したパウロは、彼らが拝んでいる人間が造った神と、人間を造った真の神の違いを明らかにしてゆきます。
(1)「この世界とその中にあるすべてのものをお造りになった神」(24)
パウロはまず、「天地の主」(24)である神は、人の「手で造られた宮にはお住みになりません。」(24)と偶像の空しさを指摘します。岡山の川口建材店の初代社長は神棚にお供えをしていたところへ、日曜学校から帰って来た孫が、「おじいちゃん、神様はそのような小さな箱に入りきれるの?」と言った言葉に心が動かされて、初めて教会に行きました。そこで、人間が作った神と人間を造られた神がおられることを知り、結果、全家クリスチャンになり、現在も親族は岡南教会の教会員として、また岡山ギデオン協会の中心メンバーとして励まれ、活ける神の証人として用いられています。
天地を造られたお方が太陽や月を輝かせ、収穫を与えておられるので、太陽、月を造られた方を差し置いて、太陽や月を拝むことは造り主に対して大変失礼なことです。
(2)「人の手によって仕えられる必要もありません。」(25)
天地万有を造られた神様は、人から得ようとしているのではなく、恵みの倉を開いて喜んで与えてくださる方です。ここに人が作った宗教と、人を造られた真の神の違いがあります。人が作った宗教は、その神に物品を与えなければなりません。また精神修養をして自分を高め良いものを与えなければなりません。そのようにして何かをすることで神を喜ばせてご利益を得るというものです。けれど、天地万有の造り主は、愛の対象として人を造られたので、人から何かを得る必要がありません。むしろ、喜んでその人の必要に応えて下さり、しかも、不信仰と罪の中にいる私たちにさえも、恵みを与えてくださるお方です。
ルカによる福音書15章にでてくる息子は、父親から受け取った莫大な財産を瞬く間に使い果たし、放蕩の末豚飼いになり、豚が食べているイナゴ豆が食べたいと思うほど落ちぶれて、そこで初めて自分の哀れな様に気が付きました。
自分の姿に気が付いた息子は、その時になって、生まれ育った父の家の豊かさに気が付いたのです。自分の欲求を満たそうとして行き着いた所が、飢えと渇きのど真ん中でしたが、彼はそこで初めて、自分の願望を満たす生き方の空しさと、父の家のすばらしさに気づいたのです。彼は目からうろこが落ちるが如く、今までの生き方から大きく方向転換をして、父の家の方に向かって歩き始めます。お土産を持って帰ってくるどころか、父親から分捕るかのように持ち去った財産は全て使い果たし、ボロボロになった息子でしたが、父はその姿を一目見るなり、走り寄って彼を迎え入れ、しかも、宴会まで開いて息子の帰りを喜び迎えいれたのです。天の父なる神様もまたこの父親のように、人を愛するものとして造られました。「私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、宥めのささげ物として御子を遣わされました。ここに愛があるのです。」(ヨハネの手紙第一4章10節)
(3)「もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともある。」(27)
神様は人間がご自分を知ることを願っておられ、ご自分を求めて欲しいと願っておられます。ですから、真に求める人に対して、ご自身を見出すように導びかれます。ピりピ人への手紙には「そして、それを得るようにと、キリスト・イエスが私たちを捕らえてくださったのです。」(3:12)とも書かれています。「神は私たち一人ひとりから遠く離れてはおられません。」(27) 「私たちは神の中に生き、動き、存在している」(28)のです。
パウロはさらに、多くの神々に礼拝をささげるアテネの人たちに向かって言っています。「このように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで造ったものと同じであると、考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも、すべての人に悔い改めを命じておられます。」(29,30)と。このパウロのメッセージに対してアテネの人たちの反応はどうだったでしょうか。「ある人たちはあざ笑ったが、ほかの人たちは「そのことについては、もう一度聞くことにしよう」(32)と言いました。では、あなたの反応はどうでしょうか。