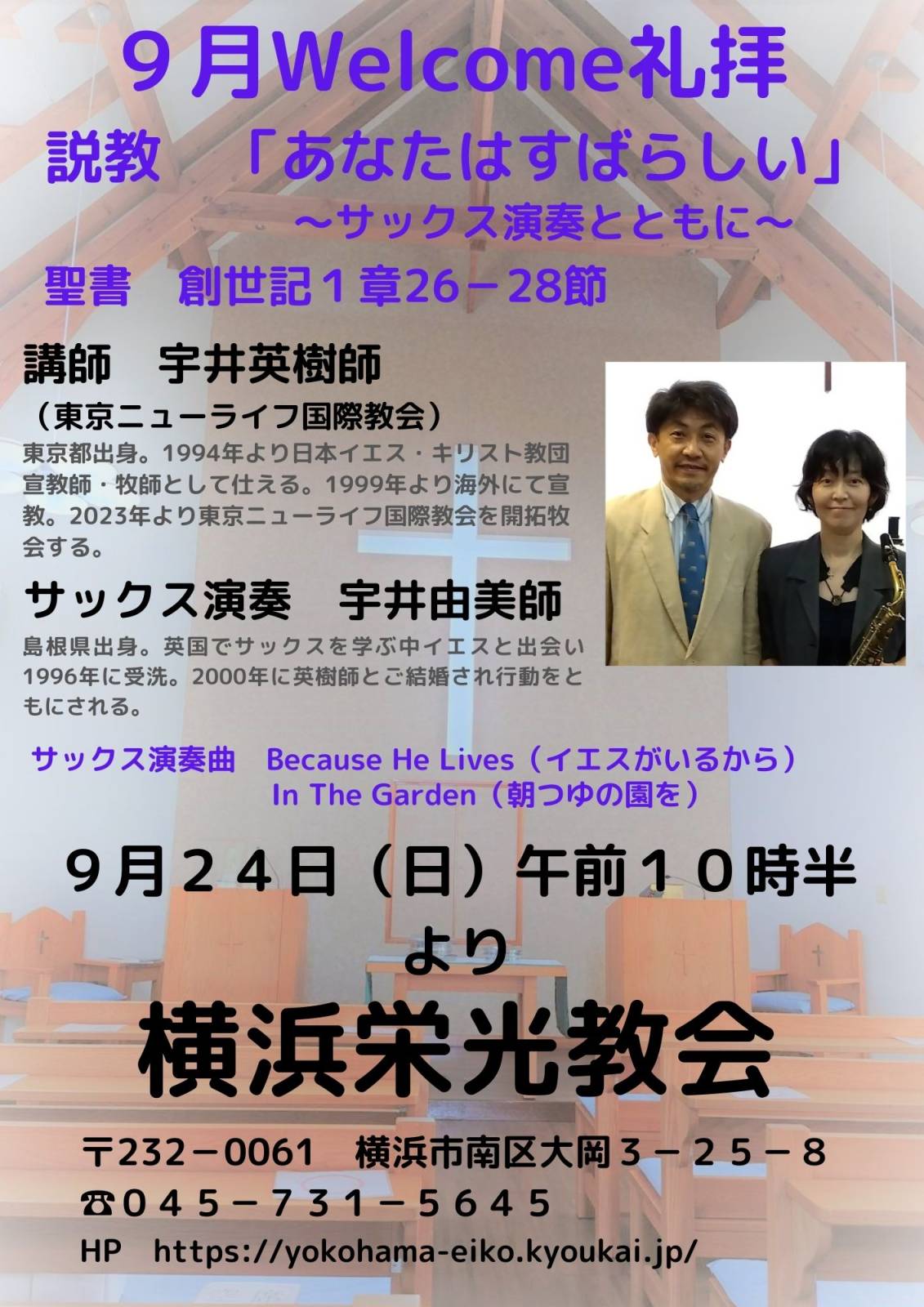「主のしもべ」
-エペソ人への手紙(16)-
聖書:エペソの手紙6章5-9節(新p391)
メッセンジャー:高江洲伸子師
しもべたち
5節の「奴隷」は、6節では「しもべ」と訳されています。奴隷もしもべも観念的にはあまり違いはないように思えますが、パウロは当時の奴隷制度の中にあるキリスト者を覚えながら、この手紙を書いていることは明らかです。
当時ローマ帝国内には、推定六千万人の奴隷がいたと言われます。帝国内のあらゆる仕事は彼らによってなされ、医師や教師さえ奴隷だったと言われています。奴隷は人権は全く認められていず、主人は奴隷に対して生殺与奪の権をもっていました。キリストの福音はその奴隷階級にも浸透してゆきました。けれど、福音は社会制度から改革に着手したのではなく、心の変革からそのわざを始めたのです。
イザヤ書61章で預言された、「捕らわれた人には解放を、囚人には釈放を告げ、…」(1)の解放は、主イエスの到来とともに始まり(ルカ4:18-21)、解放された神の民と神の家族には、新しい秩序が知らされる必要がありました。ローマの制度の中では「奴隷」という立場にあったキリスト者も、イエス・キリストにある神の民は、みな主の囚人であり、また、真の意味での自由人となりました。パウロはコリント人への手紙第一7章で、「主にあって召された奴隷は、主に属する自由人であり、同じように自由人も、召された者はキリストに属する奴隷だからです。」(22)と言っています。
ルターは「私は誰の奴隷にもならないが、全ての人の僕である」と言いました。そこにはもはやしもべも無ければ主人もない。ただあるのはキリストを長子とした兄弟姉妹関係だけなのです。したがって、主のしもべは常に「人にではなく主に仕えるように、喜んで使え」(7)、神のみこころを実践するのです。
イスラエル民族のエジプト脱出は、パロの支配のもとで奴隷として負わされていた過酷な労働からの解放だけではありませんでした。それは、彼らが本来の在り方に戻り、主なる神に仕える民となるためでした(出エジプト3:12)。
世と肉の支配からイエス・キリストの十字架によって脱出させられ、神の国に属する者となった神の民は、世にあっても、社会的な立場や地位に縛られ、人を偏り見ないようにしなければなりません。「主は人を差別なさらない」(9)からです。神は必ず、それぞれの働きに応じて報いて下さるお方です(8)。パウロはローマ人への手紙2章6節においても、「神は、一人ひとり、その人の行いに応じて報いられます。」と言っています。
主人たち
「主人たちよ。あなたがたも奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことはやめなさい。あなたがたは、彼らの主、またあなたがたの主が天におられ、主は差別なさらないことを知っているのです。」(9)というパウロの勧めは、奴隷制度が当たり前だった当時の人たちには考えられない言葉であり、思想でした。それは、主イエス・キリストの恵みに与った者でなければ理解できない言葉でした。
当時の人たちが自分と奴隷とが全く同じ立場に立っていることを認めるということは、奴隷制度そのものが崩壊してゆくことに他ならないことだったのです。けれど、キリスト者は当時すでに「主は人を差別なさらないことを知って」いました。
主のしもべ
最後の晩餐の夜、主イエスは席から立ち上がり、上着を脱ぎ、手ぬぐいをとって腰に巻き、それから水をたらいに入れて、弟子たちの洗い、腰に巻いた手ぬぐいでふき始められました(ヨハネ13:4,5)。これがキリスト・イエスにある神の国に属する者たちの指導者の真の姿です。
主の母となったマリアは、受胎告知を受けた時、「私は主のはしためです。どうぞ、あなたのおことばどおり、この身になりますように」(38)と応答しました。ここでの「はしため」(デューロス)は「奴婢」とも訳され、女奴隷を表すことばですが、マリアは主が彼女を必要とされた時、自らを主の「女奴隷」としてその身を差し出したのです。
使徒パウロは、ローマの市民権を有するエリートでしたが、復活の主に出会って、自分のことを「キリスト・イエスの囚人」(3:1)とまで言っています。
私たもまたキリストのしもべとして心から神のみこころを行い、人にではなく主に仕えるように、喜んで使える」(6,7)者とされようではありませんか。
参考図書: 工藤弘雄著「高度を上げよ」、新聖書講解シリーズ8佐布正義著「エペソ」