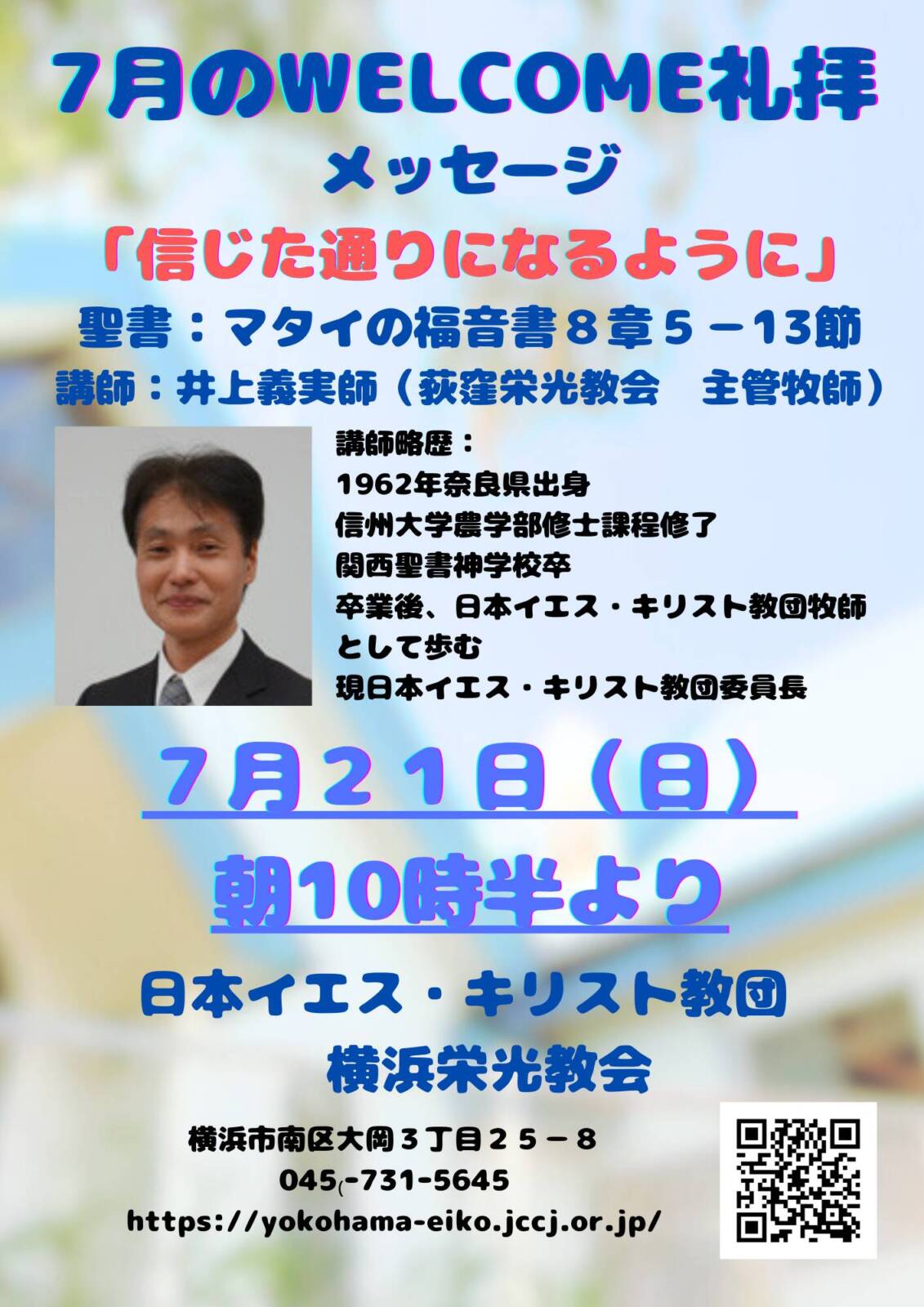『祈りのこたえ』
聖書: マタイの福音書15章21-28節(新p31)
メッセンジャー:高江洲伸子師
主イエスが「ツロとシドンの地方」(現在のレバノン)に来たとき、突如、一人の女性が現れて大声で叫びはじめました(21,22)。 彼女は悪霊によって苦しんでいる娘を癒してほしかったのです(22)。 結果、イエス・キリストはこの女性の信仰を賞賛され、娘を癒されました。主が賞賛されたこの女性の信仰とはどのような信仰だったのでしょう。
1. 熱心に求めた。
「『娘が悪霊につかれて、ひどく苦しんでいます。』と言って叫び続けた。」(22)
この女性は異邦人でしたが、キリストに、「主よ、ダビデの子よ。」(22)と言って近づいてきています。この時点でこの女性はすでにキリストを信じています。「この方なら娘を救ってくださる」という確信をもってキリストのもとに来ていることがわかります。けれども、イエス・キリストはこの婦人に対してとても冷ややかでした。「しかし、イエスは彼女に一言もお答えにならなかった。」(23)。それだけでなく、弟子たちまでも、「あの女を去らせてください。」(23)と言っています。しかも、やっと発せられた主イエスのお言葉は、「わたしは、イスラエルの失われた羊たち以外のところには、遣わされていません」(24)でした。即ち、異邦人であるあなたの願いをきくことは考えていない、と言う否定のことばだったのです。
2.粘り強く全幅の信頼をもって、求め続けた。
「しかし彼女は来て、イエスの前にひれ伏して言った。『主よ、私をお助けください。』」(25)キリストの冷ややかな対応に対してこの女性は、なおも、キリストに求め続けています。
この時のイエス・キリストのこの女性に対する対応の仕方は、あきらかに今まで出会った人たちに対する対応と違っていることに気が付きます。
ルカによる福音書11章でイエス・キリストは、祈りについて教えられています。例えば、夜中にパンを求める友人に対して、「友だちだからというだけでは、起きて何かをあげることはしないでしょう。友だちのしつこさのゆえになら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。」(8)と言っていますし、18章では、不正な裁判官に正しい裁きを求めて訴える女性に対する裁判官の心情を、「私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、このやもめは、うるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないと、ひっきりなしにやって来て、私は疲れ果ててしまう」(4,5)と吐露させ、粘り強く求め続ける祈りの効用を知らしめています。まして、ここで、ひるむことなく願いを訴え続けるツロフェニキアのこの婦人のキリストに寄せる期待は、真夜中にパンを求めてきた友人や、正しい裁判を求めてきた女性の思いに匹敵する、あるいはそれ以上のものであることを、キリストはご存じの上での冷たい態度でした。その時のキリストのみ思いを考える時、否定の中に隠されている、その奥の思いを考えないわけにはいきません。否定的態度をとり続けるキリストの思いと共に、それでも、求め続ける女性の願いの動機を知る必要があります。
今彼女の大切な娘はひどく苦しんでいるのです。この女性はどうしてもキリストに愛する娘を癒してもらわなければならないという、引こうに引けない事情があったのです。私たちは祈りについて、少し祈って反応がないと、その祈りは「み心でなかった」と足早に結論づけて、簡単に祈りの座から立ち去ってゆくことがあります。祈りの答えの遅延は、そのような私たちの動機や願いの不真実さをふるいにかけることになり、結果、隠れていた不信仰や、卑しい思いが暴露されることがあります。また、不必要ならば求めそのものが消えてゆくこともあるでしょう。逆に、どうしても祈らずにはおれない愛に気づくこともあるでしょう。祈りの背後に、神様ご自身が働かれて、私たちを求めさせようとして切羽詰まった状況へと追いやってくださることもあります。ピりピ人への手紙2章13節では、私たちのうちに働きかけて願いを起こさせる神について、3章12節では、与えようとして追い求めさせてくださる神様でいらっしゃるとも書かれています。キリストに否定されているかのように見える状況や、冷ややかなあしらいは、あるいは、祝福の前触れをであるかもしれないのです。
3.砕かれた心で求めた。
続いて、イエス・キリストのみ口からでてきたことばは、「子どもたちのパンを取り上げて、小犬に投げてやるのは良くないことです。」(26)でした。この言葉に対してこの女性は、「主よその通りです。ただ、小犬でも主人の食卓から落ちるパン屑はいただきます。」(27)と答えています。ここでの「子どもたち」は、イスラエルの民、「小犬」は異邦人のこの女性のことです。この背景には、歴史的経緯があって、民族的に距離を置いていたことによるもので、決してイエス様ご自身にそのような差別的な意識があったわけではありません。けれども、女性自身は古くからユダヤ人から民族的にそのようにみられていることは知っていたにも関わらず、ユダヤ人のイエス様の前に飛び出すように娘の癒しを願ったのです。今でしたら民族紛争にもなりかねないことばを言われたにも関わらず、「小犬でも」と、機知に富んだことばで応答する女性の柔軟な姿勢、どこまでのキリストの御前に謙って近づく姿に、キリストは、「女の方、」(28)とこの女性を尊び、「あなたの信仰は立派です。あなたが願うとおりになるように。」(28)と、祝福のことばを投げかけられたのでした。そして、その母親の信仰によって祈りはきかれ、その時、「彼女の娘は、すぐに癒された。」(28)のです。
ローマ人への手紙4章16節は、「そのようなわけで、すべては信仰によるのです。・・・約束がすべての子孫に、すなわち、律法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるのです」と書かれています。栄光教会の一人一人が、信仰の祖とされたアブラハムが受けた祝福を溢れるばかりに受ける新約の聖徒とされますように。