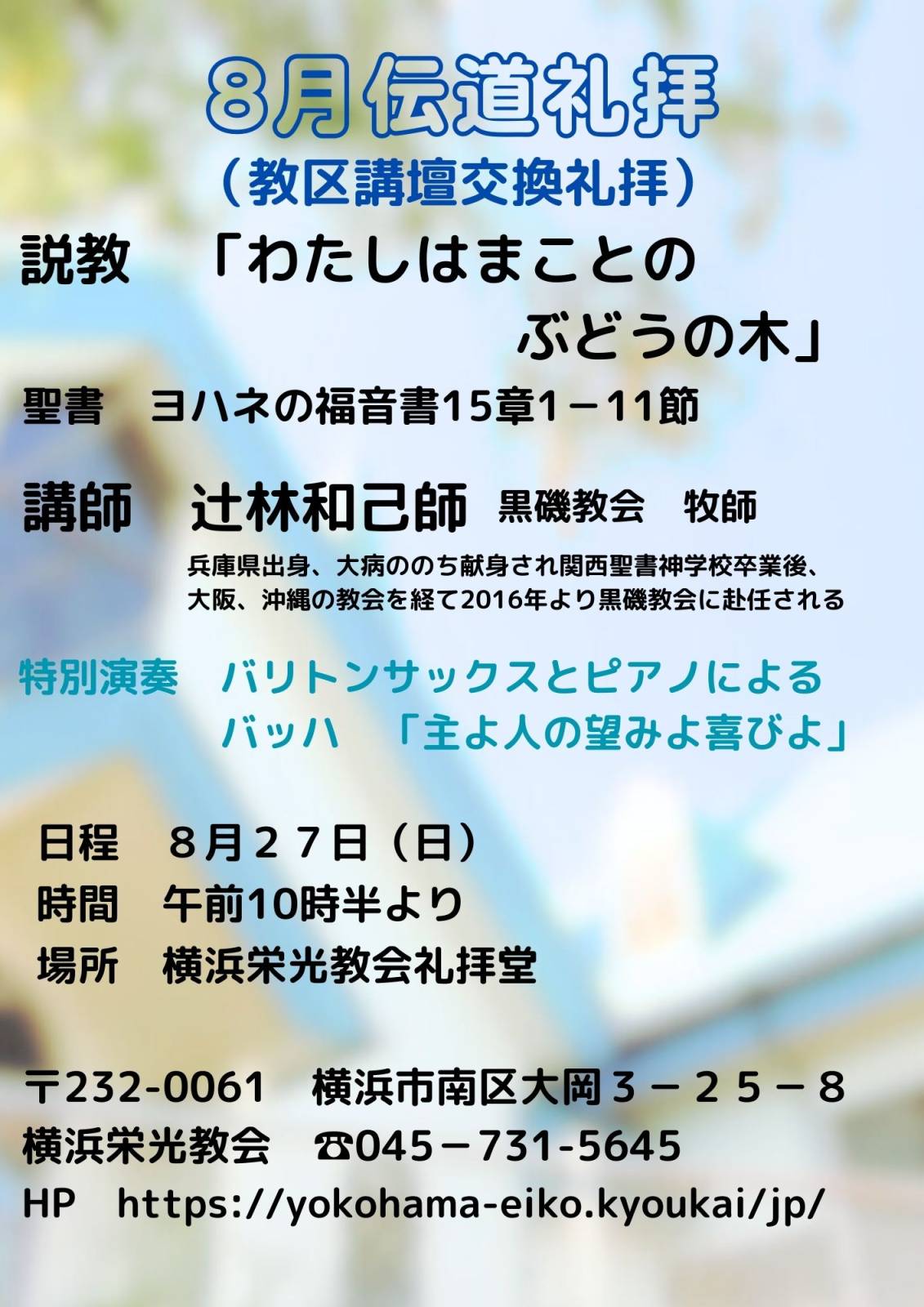「父と子」
ーエペソ人への手紙(15)ー
聖書:エペソの手紙6章1-4節(新p391)
メッセンジャー:高江洲伸子師
「子どもたち」
「父と母を敬え」これは十戒の第五の戒めです。「そうすれば、あなたは幸
せになり」、地上で長生きする(6:3)と祝福が約束されています。
家庭生活で父親は神のイメージを伝達する媒介ともされていて、子どもは父
によって神の存在を直接的に示されると言われます。例えば、父親がナイフ一
本でおもちゃを作って与える時、子どもは父の中に創造主のイメージを見、真
っ暗闇の中でも自分を守ってくれる父親の中に、神の保護を覚えると言うので
す。こうして子どもは父親を信頼し、父親に倣う者として育ち、父親への尊敬
と共に、そこに神へのイメージが築かれてゆくと言われています。
けれども、現代社会に於いては、全ての家庭とまでは言わなくても、家庭崩
壊の危機が潜み、離婚に至る夫婦は少なくありません。多くの子どもたちがそ
の犠牲を被っています。こうした家庭生活の中で子どもたちはすでに神をイメ
ージできない中で育っていると言えます。この子どもたちに「自分の両親に従
え」また、「あなたの父と母を敬え」と言っても子どもは「なんで?」と開き
直っても仕方がない状況とも言えます。では、どうすれば、「父と母を敬え
」、「自分の両親に従いなさい」というこのみことばを実践できるのでしょう
か。
「主にあって」
1節の命令の前に、「主にあって」との一句が挿入されています。もし、親
子関係に不具合が生じて来た場合、両親も子どもも共に神のもとに帰ることと
ころから始める必要があります。親子関係だけに限らず、私たちは、地上で起
こってくるどのような問題も、人を造られた神のもとに行くことによって、正
しい関係を構築することができるのです。
今回、黒磯教会での講壇交換の御用と共に、東北の諸教会を訪問させていた
だく恵みに与りました。その中で出会った一人の方は、子どもさんの自死とい
う過酷な試みの中で苦しまれていました。自死の原因は全て親である自分にあ
るという思いから離れることができないでいました。お話をお聞きした私もま
た、返す言葉が出てきませんでした。そこで、「祈りましょう」と、主の御前
に頭を垂れ、「神さま、この方の心の中に入っていってくださって、ご自分を
攻める心に変えて、慰めと平安な心をこの方の中に新たに造ってください」と
祈り致しました。その後、その方は「そうだ、自分を責めない、平安な心を神
様に新しく造っていただくことができればいいのだ」、と、仰っていました。
子どもの抱える課題があまりに大きく、また、たとえ課題が多いと思われるご
両親であられたとしても、まずは、神様のもとに行くことによって、新しい出
発をすることができるという希望がここにあります。全ては「主にあって」な
のです。
けれども、逆に、「もし両親が、キリストに従うことを妨害するなら、この
戒めに拘束される必要はない。神に従うことを妨げることはだれにもできない
からである。両親であるゆえに他の面では敬っていても、信仰に対する反対を
受けた場合は、よく祈って自分の信仰を貫くためにあかしをすべきである。子
を思う親ならば、いつか必ず理解してくれるはずである。」と佐布正義師は新
聖書講解シリーズ「エペソ書」の中に描き加えておられました。
「親たち」
更に佐布師は「父たち」に対して、「子供は『主の教育と訓戒によって育て
なさい』(4)と命じられている。…親は神の啓示を伝える器であることを自覚し
て、『主の教育と訓戒』を持って子どもの育成に当たるのである。親は、子ど
もを自分の所有物と見なすべきではい。子どもは神から委託された人格なのだ
から。主の啓示されたしつけと戒めに従って育てなければならない。」新聖書
講解シリーズ8p175 と、綴られています。
さらに、「子どもたちをおこらせてはいけません」(6)に対して、「自分の感
情で判断して子どもをしかる場合」と「人格を無視して、自分の願望を子ども
によって達成しようとしていることが明らかな場合」等を取り上げ、「子ども
の教育は『主の教育と訓戒』によるものであって、親自身もその対象なのであ
る。親自身も子どもと共に神のことばの真理に基づく生活を築くところに、真
の教育がある。また、子どもは自分自身の願望を達成のために存在するものだ
などと考えるべきではない。それは…、神の栄光を現わすことにはならない。
親たる者は、主の栄光を現わす教育ができるように、常に祈りつつ子どもに接
するのでなければならない。」p176と、この節を結ばれています。