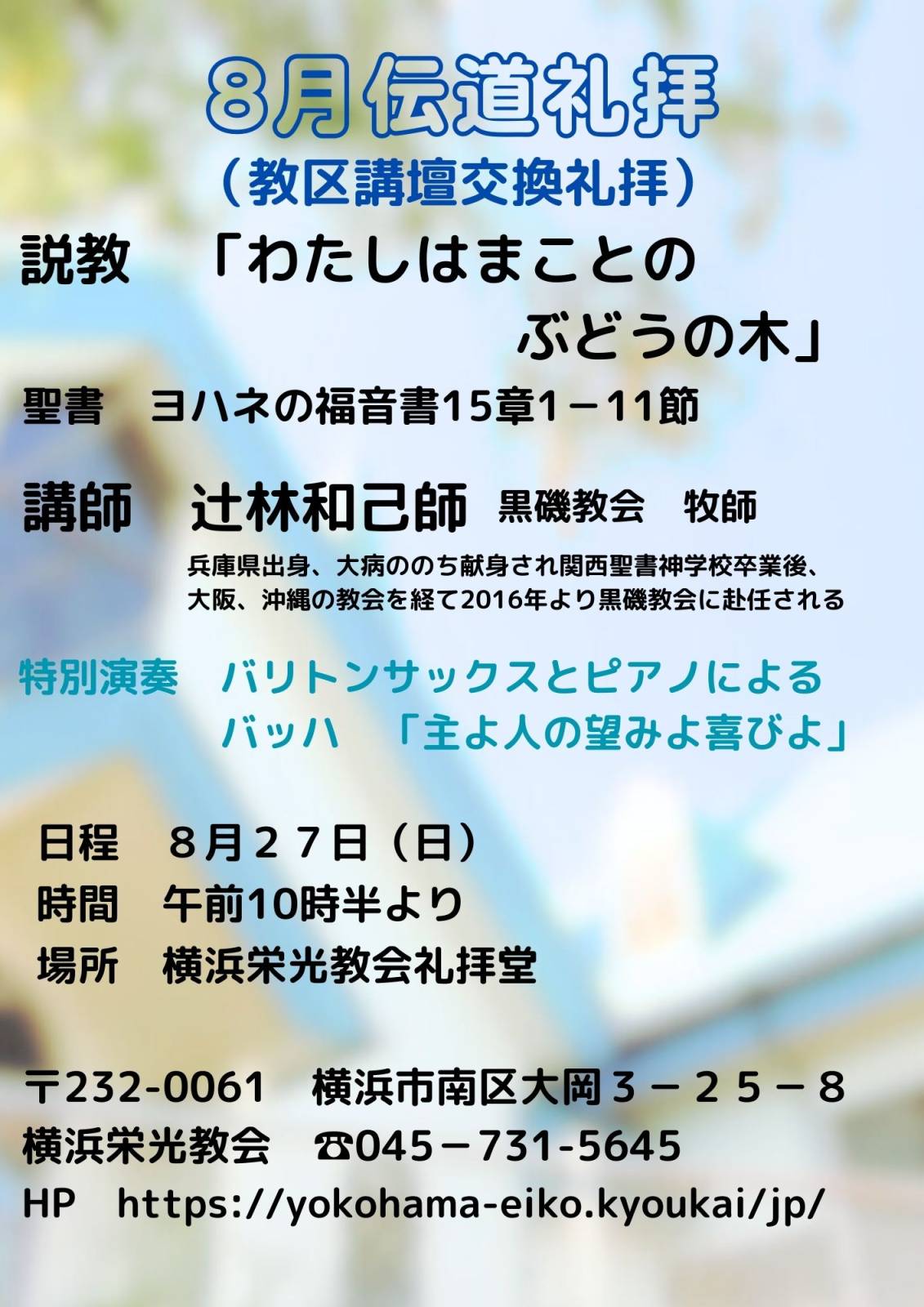「妻たちよ、夫たちよ」
ーエペソ人への手紙(14)ー
聖書:エペソ人への手紙5章21-33節(新p391)
メッセンジャー:高江洲伸子師
バックストン師は、「始祖の陥罪によってパラダイス(楽園)を失ってしまった人類に、神は主日の礼拝と家庭というパラダイスを残しておられる」と言いました。5章21節からは家庭の核とされる夫婦の関係がとり上げられています。パウロがこの手紙を書いた当時、結婚に関する倫理は極度に低く、女性や妻の地位もまた考えられないほど低かった中で、パウロは新しい「神の家族」(2:19)の在り方としての夫婦の関係を取り上げました。
妻たちよ
「主に従うように、自分の夫に従いなさい。」(22) 文語訳聖書では「主に服
(したが)うごとく己の夫に服え」、子どもたちに向かっては「順(したが)え」(6:1文語訳)という漢字が使用されています。妻が夫に従う従い方は決して子ど
もが親に従う内容と同じではないことが読み取れます。小島伊助師は、「身を委
ね託した従順さである。それも『己の夫』で、他人の夫ではない…自分の夫なの
だ。その手にあなた自身を服させなさい!」とエペソ人への講解説教「神の奥義
なるキリスト」全集4(p330)で書いています。しかも、パウロは「主に従うよう
に」と書き添えています。更に小島師は、「夫への従順の中にイエス様が意識さ
れ、イエス様が見えれば幸いである。この夫、自分自身の夫、それは一面わがま
まの原因にもなるかもしれない。しかし、自分の主人であるが、またそれはイエ
ス様との関係に響くことだとわかれば、従うことも容易だろう。コロサイ人への
手紙では『それが、主にある者にふさわしいことである。』(3:18)と言っている。
私はそこで『家庭に臨在あり』と講義した。」(全集4p440)とも。
33節の「夫が妻のかしらである」について、その理由は書かれていません。「たぶん、創造の原理からではあるまいか。アダムは先に造られ、女はあとから造られた。そして女は男に与えられた。」(全集4p441)小島師もまたこれだけの言及に留まっていました。アダムとエバの創造それ事態が、まさに、キリストと教会の予表であったと解することができます。「キリストは贖いを成し遂げて眠りにつき、そして、そのよみがえりによって教会は生じた。キリストを主とし、かしらとして、教会がからだであり半身であることは自明の理である。」それ故、「『キリストが教会のかしらである』(23)ことが、夫が妻のかしらであることのよりどころとなったのかもしれない。」とは小島師(全集4p441)の見解。
夫たちよ
夫への勧めは「妻を愛しなさい」(25,28,33)に尽きます。マケリゴット師(世界福音伝道団)は、男性の性格の弱点は愛し貫けないことであり、女性の弱点は一生かけて夫を尊敬できないことにあると言われました。妻の服従が「教会がキリストに仕えるように」でしたが、夫に対しては「キリストが教会を愛するように」妻をそのアガペーの愛をもって愛し貫きなさいとパウロは言っています。
その愛は、1.ささげる愛。キリストの愛はご自身を犠牲にし、ささげる愛だったからです。愛は惜しみなく奪うのでなく、惜しみなくささげるのです。最終的には自分の命までもです。実に男性的、意志的な愛がそこにあります。2.きよめる愛。キリストの献身的、犠牲的な愛の目的は教会をきよめて聖なるものとするためでした。その方法は「みことば」と「水の洗い」(26)。みことばは聖霊により私たちの内心をきよめます。神の言葉への応答として悔い改めと信仰による水のバプテスマがあります。キリストの教会への愛は、しみもしわもない、聖なる汚れのない栄光に輝く花嫁なる教会をご自分の前に立たせる愛なのです。夫の愛は妻の内なる人をきよめ、外なる人さえ美しくさせるのです。3.いたわり養う愛(28,29)。養いいたわる愛とは、自分のからだのように、いえ、自分のからだとして妻を愛する愛です。おなかがすけば食べ、のどが渇けば飲み、暑ければ脱ぎ、寒ければ休む、そのように自分のからだにする如く自然ないたわりと養いの愛をもって、妻を愛しなさいというのです。恥ずかしさを越えて主イエスの教会への愛に倣い、妻をいたわり養う愛が家庭生活の中に浸透します様に。4.一体の愛。「男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりは一体となるのである」(創2:24)。父母を離れて独立するのです。一体ですから共有があり、生い立ち、性格、趣味など違ったとしても愛による一体です。この一体の最高の現われは、夫婦共同の一体の祈りにあります。この祈りのために主は二人を合わせられたのかと言えるほどです。
家庭の主は神ご自身です。主にある良き妻、良き夫の規準は聖書です。
(「夫たちよ」は、工藤師エペソ書講解説教を引用させていただきました。)
参考図書 小島伊助著「神の奥義なるキリスト」工藤弘雄著「高度を上げよ」