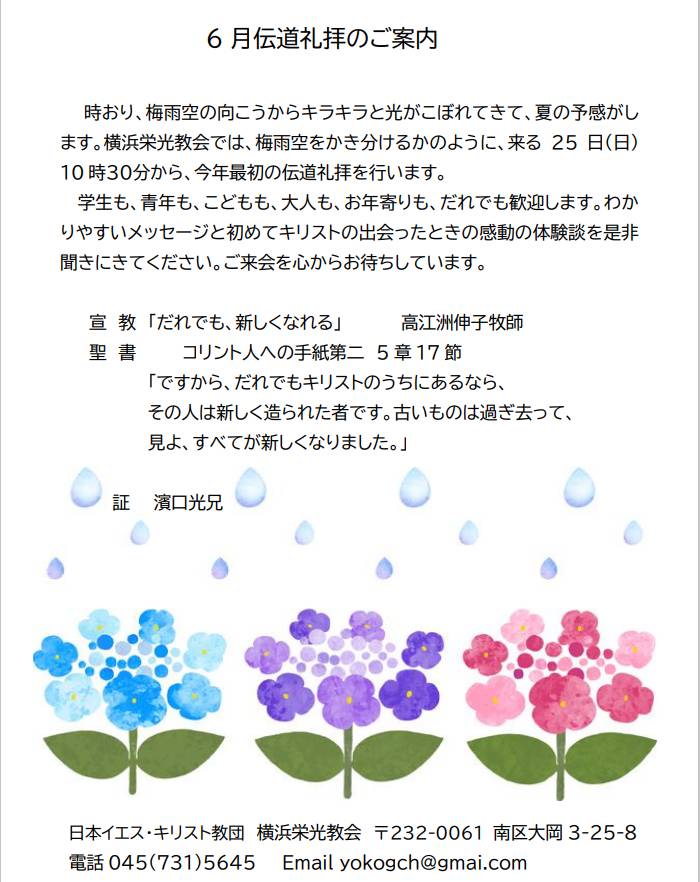「召しにふさわしく歩む」
-エペソ人への手紙(7)-
聖書:エペソ人への手紙4章1-6節(新p388)
メッセンジャー:高江洲伸子師
神様の御前にひざまずいてキリストが内に住み、キリストの愛を基とした生活を祈り勧めたパウロでしたが、4章に入り、教会内での具体的な歩み、実践を勧めます。
召しにふさわしく歩む(1)
かつて、昭和天皇が若い頃、銀座を散歩されていて、あるショウウインドウに大変興味を示され、中を覗き込まれた時、影の如く寄り添った侍従が、「陛下御身分ですぞ」と言われたそうです。まして、私たちは神の皇太子としての立場を忘れることなく、世にある生活を心に留めたいものです。世の人たちは、キリストに出会った私たちを通して天の御国に思いを馳せることでしょう。
御霊の一致(2,3)
召しにふさわしい歩みの第一の勧めは御霊の一致を保つことです。ここでパウロは一致しなさいとは言わず、「御霊による一致を熱心に保ちなさい」(3)と言っています。「熱心に保つ」には、保つ為に勤勉さが求められます。けれど、何よりも大事なことは、「聖霊による」ことです。聖霊なくして一致も、それを保つこともできないことは明らかです。そこでパウロは聖霊によってもたらされるクリスチャンの美しい5つの徳をもって一致を保つことを勧めるのです。
まず、「謙虚と柔和の限りを尽くし、寛容を示し」(2)です。謙虚は臆病になって顔色を見ながらぺこぺこすることであはりません。イザヤは神の臨在に触れたとき、内に潜む汚れと罪の様を見ることができました。自分の弱さや醜さを知る時初めて真の謙遜は生まれてきます。また、柔和と柔弱は違います。私たちは、主イエスの生き様の中に見ることができます。それは、バランスのとれた強くてやさしい心です。「寛容」とは、いつまでも忍び、広く包む心です。こうした、謙遜と柔和、寛容のあるところでは不一致にはなりません。この聖霊の賜物をお互いに求めあってゆくところから、真の教会形成の基礎はできてゆくことでしょう。
さらに「愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて」(2,3)です。聖書に書かれている「愛」の原語は神の愛を表わす「アガペー」が使われていて、他の愛との違いを示しています。それは、見返りを求めない愛です。この愛こそが聖霊の実の中でも最大の賜物です。マダガスカルや沖縄に生えている「旅人の木」は、水を求める旅人がその植物の葉柄(あるいは根)に溜まった水を飲んで癒されたところから「旅人の木」と呼ばれるそうですが、巨大な葉の柄にナイフを差し込む者に癒しの水を与えるがごとくに、クリスチャンの交わりもまた、傷を受けたところから、相手を癒す美味しい水が流れ出てくれば幸いです。
一致の基礎(4-6)
その第一は、「からだは一つ」です。キリストはかしらであり、教会はからだです。からだの器官は様々ですが、全体として一つです。
第二は、「御霊は一つ」です。御霊はからだを生かす息のようなものです。息が止まればからだは死にます。教会を生かし働く御霊は一つです。
第三は、「私たちが召された望みも一つ」です。この望みは決勝点です。教会は、贖われた世界の完成という栄光のゴールを目指して進みます。
第四は、「主は一つ」です。キリスト者の主人はイエス・キリストだけです。「主」という原語「キュリオス」はローマ皇帝の正式な呼び名でした。私たちの真の主である「キュリオス」は、イエス・キリストただ一人です。私たちはこのお方のみを拝し、愛し、仕えます。
第5は、「信仰は一つ」です。教団、教派によって信条や教理に違いはあっても、イエス・キリストへの信仰と信頼は一つです。全てのクリスチャンは、自己を放棄して、ただ主に信頼するという姿勢において一つです。
第6に、「バプテスマは一つ」です。バプテスマの方法に違いがあっても、イエス・キリストは主であり、救い主であると公に告白し表明するバプテスマは一つです。
第7に、「父なる神は一つ」です。神は父です。その父なる神は、すべてのものの上にあって支配される神、すべてのものを貫く摂理の神、すべてのもののうちにいます臨在の神なのです。
一体、一霊、一望、一信仰、一バプテスマ、一父神への生き生きとした信仰告白があるところ、教会は常に一致を保つことができます。
「召しにふさわしく歩む」とは、まさに、聖霊による一致した歩みと言えます。
工藤弘雄著「高度を上げよ」エペソ人への講解説教から