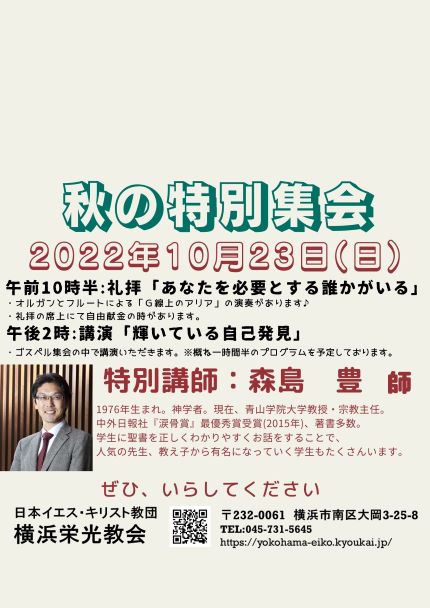「だれが救われることができるのか」
-マルコの福音書に学ぶ⑭-
聖書:マルコの福音書10章17-27節(新p87)
メッセンジャー:高江洲伸子師
再び、マルコの福音書から学ましょう。9章で「だれが一番偉いか論じ合っていた」(9:34)お弟子たちは、10章後半においても相変わらず、「一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください」(37)と、席順争いの中にあることがわかります。そこへ、突如、「良い、先生。永遠のいのちを受け継ぐためには。何をしたらよいでしょうか。」(17)と、一人の青年が瑞々しくキリストの御前に進み出たのです。
この青年は、社会的地位と豊かな財産とにめぐまれた、世にあっては、幸せな青年でした。そうであるにも関わらず、キリストのもとに更なる必要を求めて来た彼の動機は何だったのでしょうか。それは、彼が世が与える何者をもっても、真に自分の心を満たすものを得ることができていなかったからです。
数学者であり、哲学者であるパスカルという人は、「人には、イエス・キリストの形をした空洞がある」と言いました。私たち人間は、この世の何物をもっても満たされることができない心の空洞を抱えながら生きています。主イエスは、うわべだけの幸せで満足することなく、人間にとって、本当に大切なものを真剣に求めるこの青年に、慈しみの目を向けて答えておられます。
では、この青年が求めた「永遠の生命」とはどのようなものでしょう。もし、この若者が肉体の命に関する不老長寿を求めていたならば、彼は医師を訪ねたことでしょう。そうではなく、キリストの元に来たということは、この世が与えることができないところの「永遠の命」であることがかわります。
創世記2章には、「主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きた者となった」(7)と書かれています。それは、人は神から与えられる霊的生命によって生かされるのでなければ、真に生ていることにはならないことを指しています。そして、この青年もまた、自分は世にあっては全てのものを持っているものの、真の命である永遠の命をまだもっていないことに気がづいたので、キリストのもとに「永遠の命」を求めて来たのでした。
キリストもまた、このまじめで熱心に道を求めてきた青年を慈しんでおられます(21)。けれど、決して曖昧な言葉で本筋を逸らすことなく真実に答えられたのでした。
例えば、もし、誰かが、誰かの命を救おうとしているならば、自分の生命を犠牲にすることも覚悟しなければならないことがあるでしょう。逆に、永遠の生命を受ける側においてもまた、自分を捨てることの覚悟は必要です。この青年は自分でも言っているように、教育熱心な家庭に育ち、幼い時から神のおきてを忠実に守ってきた模範青年でした。しかし、この若者が真のキリストの中にある命を得ようとするならば、彼自身もまた、利害打算をこえ、すべてをかけて、キリストの言葉に従おうとする気構えは必要とされるでしょう。けれど彼は、今自分の魂を満たしていないその生活を手放すことなく、その上に神から来る霊的生命を求めようとしていたのです。このような求め方は、今手にもっているものを持ちながら、もっとあれもこれもと求める、子どもの様な求め方でしかありません。
同様に、私たちもまた、生きて行くために、信仰は必要であることはわかっていても、何かを犠牲にしてまで、それを求めようとはしません。手放すことよりもそこから更に+αして、もっているが上にも更に加えようと、自分本意な期待をしているのです。
主イエスは、「永遠のいのちを受け継ぐためには、何をしたらよいでしょうか。」と近づいてきた青年を慈しみつつも、きっぱりと、「かえって、あなたが持っている物をすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。そのうえで、わたしに従って来なさい。」(21)と言われました。持っている物全てを貧しい人たちに与えるということは、律法の全てを守ることよりもはるかに難しく、文字通り「らくだが針の穴を通る」ことよりも難しいことでした。青年が悲しみながら立ち去ったのは当然のことです。
「それでは、だれが救われることができるでしょう。」(27)と驚く弟子たちに、主イエスは、「それは人にはできないことです。しかし、神は違います。神にはどんなことでもできるのです。」(27)と言われました。その主は(やがて)私たちの内に潜む自己中心の罪をも全て赦され、神のご目的に適う人として生きる者とされるために、ご自身の全て、いのちまでも十字架にお捨てくださるのです。