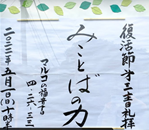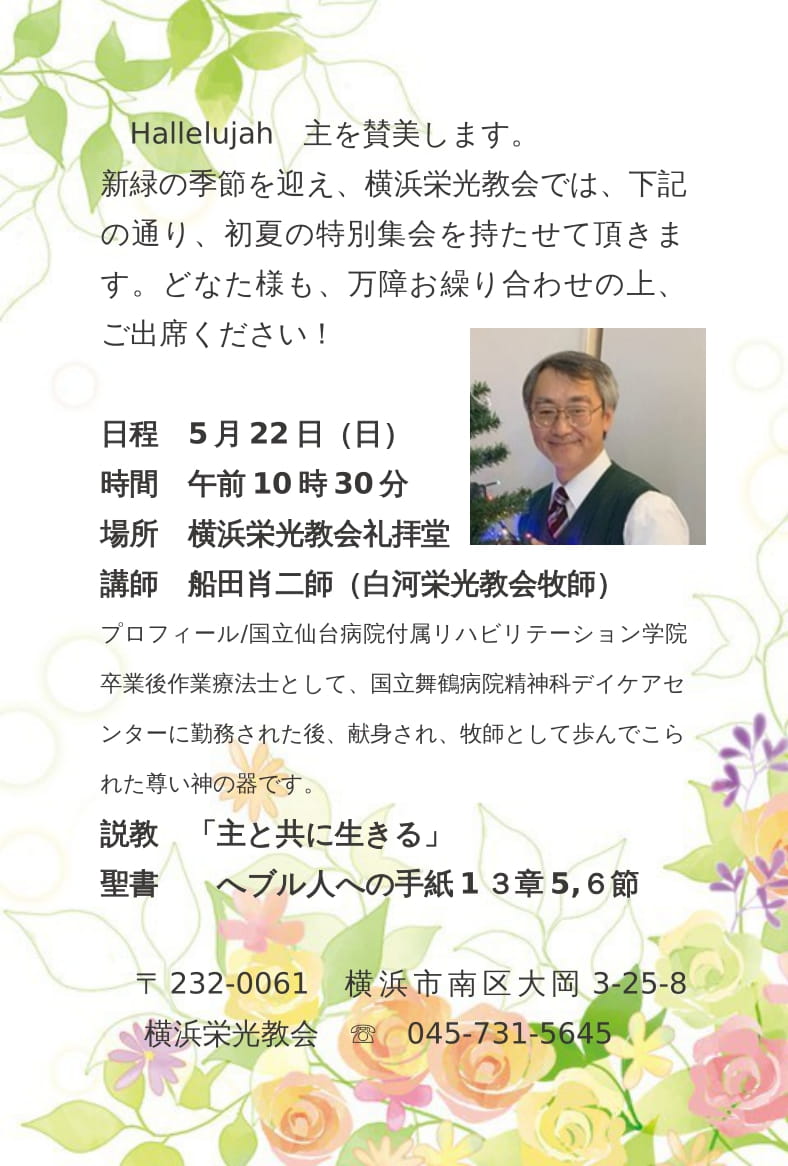「どうして怖がるのですか」
– マルコの福音書に学ぶ-⑦
聖書 : マルコの福音書4章35-41節
メッセンジャー:高江洲伸子師
ゴールデンウイークは如何だったでしょうか? 私は29日、関東教区全教会の集いで、講師の臼田尚樹師からペテロ書を通して幸いなメッセージを頂きました。3日からは、ズームで塩屋聖会に参加させて頂きました。集会、聖会で講師の方々から取り次がれるメッセージは、終わりの時代への備えに関するものが多くありました。自然災害、経済、昨今起こって来る凶悪犯罪等、世相が急激に変わってきている様を、感知している人は少なくないでしょう。こうした状況下で、本当に安心して身を任せることができるものを私たちはもっていたかどうかを再確認する時を迎えているのかもしれません。
聖書に出て来るキリストの弟子たちは、イエス様さえ一緒にいてくだされば鬼に金棒と思っていたかもしれません。ところが、ガリラヤ湖の船中で、突然嵐に見舞われて、波が舟の中にまで入ってきて、今にも沈みそうな中で、肝心の頼りとしていたイエス様は、舟の後ろの方で眠っていたのです。弟子たちはどんなに驚いたことでしょう。水しぶきがイエス様のお顔やお体にかかっていたことでしょう。それにも関わらず、イエス様は眠っておられたのです。
そこで弟子たちは、慌てて、「先生、私たちが死んでも、かまわないのですか」(38)と、イエス様を起こします。その弟子たちの声に、イエス様は、やわら起き上がり、ナント、風が吹きつけ、高波が押し寄せている湖の方を向いて、「黙れ、静まれ」(39)と言われたところ、「すると風はやみ、すっかり凪になった。」(39)。のです。驚いている弟子たちにイエス様は、「どうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですか。」(40)と言われました。私たちからすれば、嵐の中で眠っていることの方が普通ではありません。いったい、イエス様が私たちに与えようとしておられる信仰とはいったいどのようなものなのでしょう。すぐ側で侵食を共にしていた弟子たちでさえ、「彼らは非常に恐れて」「風や湖までが言うことを聞くとは、いったいこの方はどなたなのだろうか」(41)と、互いに言ったと、マルコは書いています。
この箇所は、先週のからし種の話の続きに書かれています。先週は、信仰は種が成長して実を結ばせてゆくように、成長してゆくものであることを知りました。
マタイの17:20には、「あなたがたの信仰が薄いからです。まことに、あなたがたに言います。もし、からし種ほどの信仰があるなら、この山に『ここからあそこに移れ』と言えば移ります。あなたがたにできないことは何もありません。」(マタイ17:20)とも書かれているところから、イエス様は、弟子たちが如何にイエス様を信じる信仰の内容が薄いものであるかをご存知の上で、山をも動かすほどの信仰を抱かせるべく、訓育されていることを福音書は端々書いています。特にガリラヤ湖上の突風がその信仰の弟子訓練の為によく用いられてもいます。
マルコはこの4章に続いて、6章でも、よく似た記事を書いています。それは、パンの奇跡が行われた直後のことでしたが、イエス様は弟子たちを「無理やり舟に乗リ込ませ、向こう岸のベッサイダに先に行かせて、」(45)ご自分は、「祈るために山に向かわれた。」(46)箇所。イエス様が弟子たちの信仰の為に祈りつつご訓練されている様子がよく伺えます。弟子たちを乗せた舟が丁度湖の真ん中あたりに来た夕方頃、舟は逆風に遭遇します。漕いでも進みません。その災難の中で弟子たちは、岸辺にいたはずのイエス様が、湖の上を歩かれているのを見て幽霊だと思い、おびえて、叫び声をあげます。屈強な漁師だった弟子たちです。その弟子たちにイエス様は「しっかりしなさい。わたしだ。恐れることはない」(50)とお声をかけられて、弟子たちが乗っている舟に乗り込まれると、風はやんだのです。その時も、「彼らはパンのことを理解でず、その心は頑なになっていたからである。」(52)とマルコは書いていますが、イエス・キリストが神ご自身でられることの認識の低さに驚きます。あの12弟子でさえ、信仰のあり方はこのようでした。まして、私たちがどこまで、イエス様を神ご自身として認識しているかが問われます。向後昇太郎という神学校の先生は、神学生に向かって、「試されない信仰と嘘つきのうそほどあてにならないものはない。」と、常々仰られていました。真にそうです。私たちの信仰は試されると藁のように燃えてなくなることさえあります。
「激しい突風」は、「暴風」「地震」とも訳せる言葉です。「私は大丈夫」と思うところを自戒しつつ、災難や艱難のさ中で信仰の勝利を得る者へと、日々与えられる信仰のご訓練を軽んじることなく、育てていただき、イエス様が眠っている様に見えても、向こう岸におられても、必要な助けは来ると信頼できる者へと。